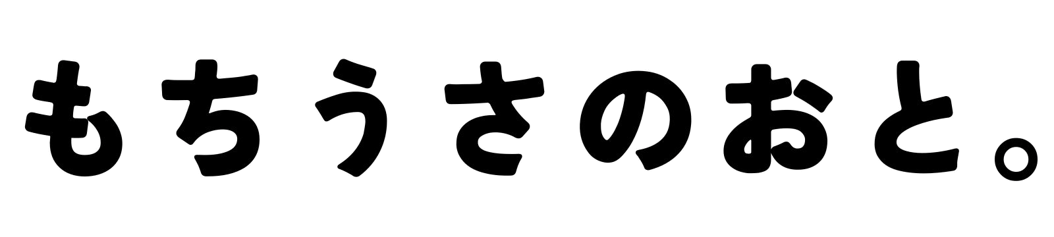最近、SNSやニュースで「パパの育休」が取り上げられる機会が増えました。
背景には、政府の少子化対策や育児への男性参加を促す動きがあります。
特に2022年から始まった「産後パパ育休制度」は、多くの企業に制度整備を促し、実際に育休を取る男性が少しずつ増えてきています。
また、コロナ禍をきっかけにテレワークや家庭での時間が見直されたことも、育休への関心を高めた一因といえるでしょう。
とはいえ、育休を取ることに対して「仕事に支障が出るのでは?」「周りの目が気になる…」といった不安を持つパパも多いはず。
そこで本記事では、育休を実際に取得したパパたちのリアルな体験談をもとに、育休のメリット・デメリットをわかりやすく紹介していきます。
「家族のために何ができるか」「育休後のキャリアはどうなるのか」など、気になるポイントを丁寧に解説していきますので、これから育休を検討している方の参考になれば幸いです。
パパが育休を取るメリットとは
家族の絆が深まる時間が持てる
育休を通じて得られる最大のメリットのひとつが、家族と過ごす時間です。
朝から夜まで赤ちゃんと向き合うことで、泣き方の違いやミルクの時間、寝かしつけのタイミングなど、育児のリズムを肌で感じることができます。
たとえば「パパがミルクをあげるとよく飲んでくれる」「お風呂はパパ担当にすると寝つきがいい」など、小さな成功体験を積み重ねることで、自信にもつながります。
家族との時間を共有することで、子どもとの距離もぐっと縮まり、「自分も育児の当事者だ」と実感することができるでしょう。
ママの育児負担が軽減される
出産後のママは、体の回復が追いつかない中で、昼夜を問わない育児に追われがちです。
そこにパパが育休を取り、日々のオムツ替えや寝かしつけ、家事などを一緒に担うことで、ママの負担は大きく軽減されます。
「パパがいるだけで安心できた」「一人で頑張らなくていいと思えた」といった声も多く、夫婦の信頼関係がより強くなるきっかけにもなります。
産後うつのリスクを減らすという意味でも、パパの育休は大きな役割を果たしています。
子どもの成長を間近で感じられる
生後数ヶ月は、子どもの成長が目に見えてわかる貴重な時期です。
初めて笑った日や、寝返りができた瞬間など、一つひとつがかけがえのない思い出になります。
仕事に追われていたら見逃していたかもしれない瞬間に立ち会えるのは、育休を取ったパパの特権です。
「初めて“パパ”って呼ばれたとき、涙が出そうになった」と語るパパも。
子どもとの絆を築く大切な時間を、一緒に過ごせることは何ものにも代えがたい経験になるでしょう。
実はある?パパ育休のデメリット
職場での理解が得られにくいことも
制度としては整ってきたものの、実際に育休を取得しようとすると「本当に取るの?」「戻ってこれるの?」といった声が聞こえることもあります。
特に中小企業や男性社員の育休取得が少ない職場では、前例がないことがネックに。
「迷惑をかけるのでは」と心理的なプレッシャーを感じるパパも少なくありません。
育休を取ったパパの中には、「職場の空気に負けそうになったが、家族のために踏み出した」と語る人も。
制度と実態のギャップは、まだ完全には埋まっていないのが現状です。
キャリアへの影響が気になる
数ヶ月とはいえ職場を離れることに対し、「昇進が遅れるのでは」「ポジションがなくなるのでは」と不安を抱く人もいます。
特に管理職やリーダー職に就いている場合は、業務の引き継ぎや復帰後の調整が必要になるため、なおさら心配に。
「同僚が担当していたプロジェクトに戻れず、少し疎外感を感じた」と話すパパもいました。
会社の制度や上司との事前の話し合いがカギになる部分です。
育休中の過ごし方に戸惑う声も
いざ育休を取得しても、何をどうすればいいのか戸惑うケースもあります。
特に初めての育児の場合、「赤ちゃんとどう接すればいいかわからない」「毎日が同じことの繰り返しで、自分の役割が見えない」といった声も。
家事も育児もママの方が慣れているため、遠慮してしまいがちになるのもパパあるあるです。
「最初の1週間は正直きつかった。でも、毎日続けるうちに自分なりのペースができた」といった体験談からも、慣れるまでは思った以上に大変なことがうかがえます。
先輩パパたちの体験談と工夫
実際に育休を取ったパパの声
「育休中は大変だったけど、取ってよかったと思える瞬間が多かった」と話すのは、2児のパパであるKさん。
最初はオムツ替えもおっかなびっくりだったそうですが、1ヶ月もすれば「泣き方で空腹か眠いかが分かるようになった」とか。
別のパパは「夜中の授乳で寝不足になったけど、赤ちゃんが自分に安心して眠る姿に癒された」と語ってくれました。
職場の理解を得るまでは不安もあったものの、「家族のために踏み出したことに後悔はない」と笑顔を見せる人が多く、リアルな声には説得力があります。
不安を乗り越えるための準備
育休取得に踏み切る前に、先輩パパたちが口をそろえて言うのが「事前準備の大切さ」です。
たとえば「上司や同僚に具体的な引き継ぎ資料を用意した」「復帰後のスケジュールをあらかじめ共有しておいた」など、職場との信頼関係を崩さない工夫が欠かせません。
また、自宅では「料理の練習をしておいた」「子育てに必要なグッズを揃えておいた」という声も。
あるパパは「育児本を読んで心構えをしておくと、実際のギャップが少なかった」とも話しており、精神面の準備もポイントです。
夫婦で協力し合うコツとは
「育休は、夫婦の絆を深めるチャンスでもある」と話すのは、第一子の誕生を機に育休を取ったSさん夫婦。
夫婦間で「今日の家事分担を朝に決める」「1日1回はお互いの“ありがとう”を伝える」など、小さなルールを作ることで気持ちよく過ごせたといいます。
また、家事や育児を完璧にやろうとせず、「できることからやる」「相手のやり方を否定しない」といった姿勢も大切。
お互いに負担を分け合い、声をかけ合うことで、ストレスを減らしながら育児に向き合うことができるのです。
まとめ
パパの育休取得には、家族の時間が増えたり、ママの負担が軽くなったりと多くのメリットがある一方で、職場の理解やキャリアへの不安といった課題も存在します。
しかし、先輩パパたちの体験談からは「準備」と「夫婦の協力」が成功のカギであることが見えてきました。
事前の話し合いや家事育児の分担、感謝の言葉を忘れないことが、育休期間を充実させるポイントです。
「育休=休み」ではなく、「家族との時間を全力で過ごす大切な期間」として向き合うことで、得られるものは想像以上に大きいのではないでしょうか。